絵本で知ろう!凸凹ちゃん
はじめまして。
発達障害児やグレーゾーンのお子さんのママの子育てを支える、子どもの発達インストラクター大橋りょうこです!

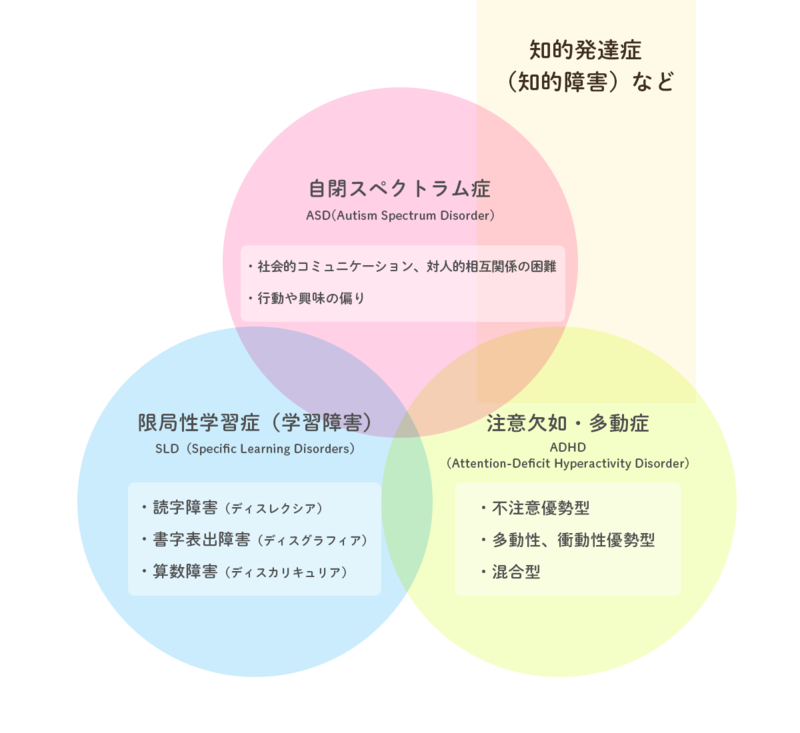
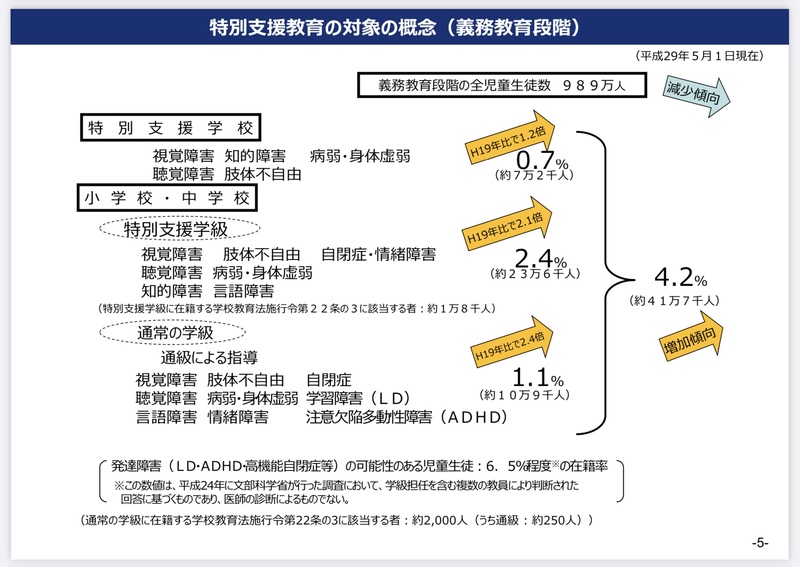
そんな絵本を、発達障害児の母である大橋りょうこが本気で選んでいます!!
この企画は「絵本シンポジウム2022〜うっかり世界平和」の中のイベントです!
「世界平和」の中に、みんな幸せになってほしい!という気持ちがあると私は思うのです。
地球に住む人間みんな誰でもなってほしいけど、いきなりドカン!と地球全土が幸せになる方法は、よくわかりません。
ひとつの種が芽を出し、木になり、実をつけ、そして、その実でたくさんの種ができる。
私もその種のように、幸せの種まきをして、少しずつでも幸せが増やせるといいなぁ!と思いました。
そこで、私はまず誰に幸せになってほしいかな!と思い浮かべたのが自分の息子でした。
息子が発達障害だと分かった時、病院の先生から「障害」の意味についてお話がありました。
この子の「障害」は「本人=“害”」ということではありません。
この子にとっての「障害」は社会の中にたくさんあるんです。
だから、「障害」をなくすために療育するのではありません。社会に出ても大丈夫なように練習しておくのです。
その一方で、周りの大人たちが、この子を理解して配慮することも「障害」が減っていくんですよ!
一緒に何ができるか考えましょう!
この言葉に私は胸が熱くなりました。
私は「障害」という言葉に抵抗がある訳ではありません。
私の父は、病気で難病に罹り、車椅子生活をしていた「障害者」でした。
およそ30年前は電車に乗るのも一苦労。
駅員さんに毎回事前に連絡をして、エレベーターのない階段を担いてもらいホームに行く。
電車の中では、狭いのに、車椅子の父がいることで余計狭くなり文句を言われたり・・・
そんな姿を見て、なんでこんなに暮らしにくいんだろうと思っていました。
でも最近は電車内には車椅子が乗れるスペースはあるし、エレベーターは各駅にありますよね!
随分と「障害」が少なくなってきました。
そう。「障害」って、周りの人の理解と配慮で減るものなのですよね!
そして、こうやって目に見える「障害」だったら、周りの人もお手伝いしやすいですしね!
でも発達障害の皆さんはどうでしょう?
見た目にはわからない方も多くいます。
一般的に、社会的に、非常識だ、と皆さんが思う行動をしてしまう方もいます。
周りの方が「その人の特性」や「なぜその行動をしているのか」を理解してもらえない限りその人の「障害」は減らないんです。
「障害」をなくすのは、本人が努力することもありますが、それと共に周りの方の理解と配慮が必要なんです!
「障害」は、その人自身が社会の中で「障害」になっているのではなく、社会の中で生きる上で困ってしまうこと、生きづらくしていること
なのです。
だから、私は、
もっと理解してくれる人を増やしたい!
お互いにできることが何かを考えたい!
そう思ってこの企画を考えました!
絵本が大好きな人も、ちょっと気になった人も、ぜひご参加ください!






